こんにちは、ネコリテです。
猫との暮らしや悩みごとについて、実体験をもとにブログを書いています。
今回は、わが家の猫に突然起きた「急性腎障害(急性腎不全)」の体験談をまとめました。
ある日、急に食欲がなくなり、尿も出ない――そんな異変から始まった、数日間の闘病記です。(現在は回復しています)
「うちの子にも同じことが起きたら…」と心配な方に向けて、見逃せない初期症状や治療の流れ、診察の内容まで詳しくお伝えします。
この記事でわかること
<前編>
- 急性腎障害、急性腎不全、急性腎臓病の違い
- 急性腎障害と慢性腎臓病(慢性腎不全)の違い
- 急性腎障害の原因は大きく分けて3種類ある
- 早期発見するためのポイント
<後編>
- 急性腎障害の治療期間と治療費用
- わが家の愛猫の体験談
※本記事は前編です。
「具体的な治療実例を知りたい」という方は
👉後編から読む
猫の急性腎障害(急性腎不全)とは?
急性腎障害は、短期間で腎機能が急激に低下する状態です。
慢性腎臓病とは異なり、早期の対応で回復する可能性があります。

よく「猫は腎臓病になりやすい」と言われているけど、腎障害・腎不全・腎臓病の違いって何だろう?
結論、どれも“腎臓の機能が低下した状態”を表す言葉です。
以前は「腎不全」という言い方が一般的でしたが、現在は「腎障害」や「腎臓病」が多く使われています。
動物病院によって呼び方が異なるかもしれませんが、私のかかりつけではこのような名称を使っていました。
急性の腎臓病→急性腎障害(旧称 急性腎不全)
慢性の腎臓病→慢性腎臓病(旧称 慢性腎不全)
個人的には、上記の名称を使っている動物病院は「きちんと最新の獣医療にアップデートしているんだな」という印象を受けて、ひとつの安心材料になります。
ただし現在でも「腎不全」という言葉を使う先生の中には、飼い主さんにとってわかりやすいよう、あえて旧称を選んでいるケースもあるかもしれません。
実際にネット検索では「急性腎不全」と表記されていることも多いため、この記事では両方の言い方を使って解説していきます。
慢性腎臓病との違い(AKIとCKD)
猫の腎臓病といえば、慢性腎臓病を思い浮かべる方が多いかもしれません。
実際、多くの飼い主さんが経験するのも慢性タイプです。
一方で、急性腎障害(旧称 急性腎不全)はあまり聞き慣れず、「愛猫が発症して初めて、慌ててネットで調べた」という方も少なくないはず。
ここでは、「急性」と「慢性」の主な違いをまとめてみました。
| 分類 | 急性腎障害(AKI) | 慢性腎臓病(CKD) |
|---|---|---|
| 症状の進行 | 突然、短期間で悪化 | 数ヶ月〜数年かけてゆっくり進行 |
| 緊急性 | 非常に高い!命に関わる | 高くはないが、症状があれば受診必須 |
| 余命・回復 | 早期治療で回復することもあるが、慢性化や命を落とすこともある | 完治しないが、ケア次第で数年生きられる |
| 特徴 | 原因によって「腎前性・腎性・腎後性」の3つに分類される。発症しやすい年齢は特になし | 10歳以上のシニア猫での発症が多い |
◆AKI=Acute(急性) Kidney(腎臓) Injury(損傷)
◆CKD=Chronic(慢性) Kidney(腎臓) Disease(病気)
急性腎障害の原因は3つに分類される
急性腎障害(急性腎不全)とは、腎臓が急にダメージを受けてうまく働かなくなる状態のことです。
まずは、腎臓の役割を簡単に説明しますね。
腎臓は、血液をろ過しておしっこを作る臓器です。
心臓から送られてくる血液には、体にとって必要な成分と、いらない老廃物の両方が含まれています。
腎臓はこの中から不要なものをおしっこと一緒に体の外へ出し、きれいになった血液をまた心臓に戻しているのです。
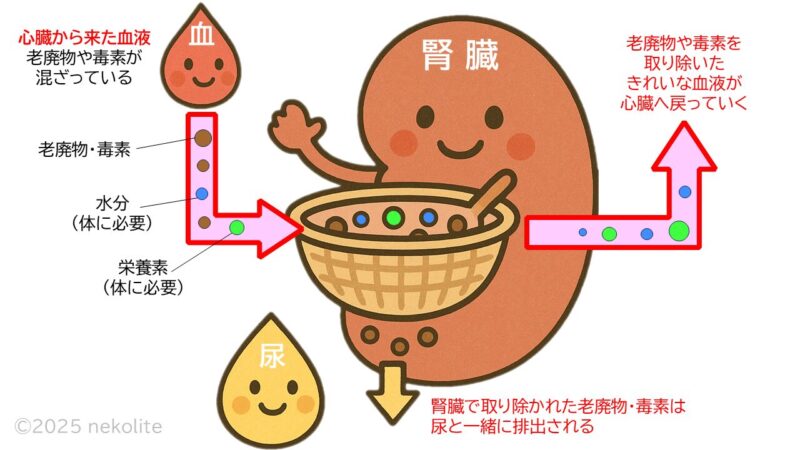
そんな大切な腎臓ですが、急性腎障害(急性腎不全)の原因は大きく3つに分類されます。
【原因】心臓の病気や脱水などで腎臓へ流れる血液が減る
【例】心不全、脱水、大量出血など
【原因】中毒や感染症などで腎臓が直接傷つく
【例】中毒、細菌感染など
【原因】おしっこの通り道がふさがれて尿が出せず、腎臓に負担がかかる
【例】尿路結石、膀胱や尿道の腫瘍など

このように、原因によって治療法は異なります。
大切なのは「どのタイプの原因で腎臓が傷ついているのか」を見極めて、その原因を取り除くこと。
それが治療の第一歩になります。
どんな症状が出るの?【おしっこで早期発見】
ある日突然食べない、動かない、おしっこが出ていない──それは猫の急性腎障害(急性腎不全)かもしれません。
この病気は進行が非常に早く、気付いた時には命に関わることもある怖い疾患です。
急性腎障害(急性腎不全)で見られるサインは、次のような症状です。
- 元気や食欲の低下
- 嘔吐やふらつき
- ぐったりして動かない
- おしっこの量が極端に少ない、または丸一日出ていない
特に「おしっこの量や回数の変化」は、早期発見の大きなヒントになります。
しかし2匹以上の猫さんを飼われているお宅では、どの子の排尿か分かりにくく、異変の発見が遅れがちですよね。
実際、わが家でも2匹の猫を飼っており、トイレは4つ。
100%確実に見分ける…ことはできませんが、それぞれの猫が「お気に入りのトイレ」を使うことが多かいため、早めに1匹のおしっこが出ていないことに気付き、早期治療につなげることができました。
猫さんの健康を守るには、「見えないおしっこ」を見える化することが重要です。
例えばシステムトイレ(=ニャンとも清潔トイレなどの2層式タイプ)を使われているお宅でしたら、「1週間取り替え不要のシート」よりも、1回の排尿ごとに取り替える安い犬用シートがおすすめです。

わが家ではこちらのシートを長年愛用しています。
ペラペラすぎず、コスパも良いのでお気に入りです。
「でも毎日シートを取り替えるのは大変…」
そんな方には、AIトイレ管理ツールがおすすめです。
✅Catlog Board(キャトログ ボード)
✅Toletta(トレッタ)
といったAIトイレ管理ツールは、おしっこの回数や量を自動で記録してくれる優れもの。
日々の排尿データを見える化することで、異変の早期発見に役立ちます。
\今あるトイレに使える/
\カメラ付きトイレ/
月額利用料がかかるなど決して安価とは言えませんが、急性腎障害(急性腎不全)のリスクや治療費を考えれば、「後で後悔しないための備え」としては十分価値はあるかなと思います。
※治療費の目安は「後編」で詳しく解説していますが、軽症でも約5万円、重症なら入院や手術で数十万円かかることがあります
猫さんは泌尿器系のトラブルが多い動物です。
だからこそ、ほんの小さな変化にも気付ける環境づくりが、愛猫の命を守る第一歩になります。
腎臓病の治療で「点滴」をする理由
急性腎障害(急性腎不全)や慢性腎臓病の治療では、点滴(輸液・補液)がよく使われます。
症状が軽い〜中程度なら皮下(皮膚と筋肉の間)から入れる「皮下点滴」、重症の場合は入院して血管から直接入れる「静脈点滴」が行われます。
皮下点滴は背中の皮下に入れることが多いですが、時間とともにお腹や足へと垂れ下がっていき、半日~24時間かけて、ゆっくりと体内へ吸収されていきます。
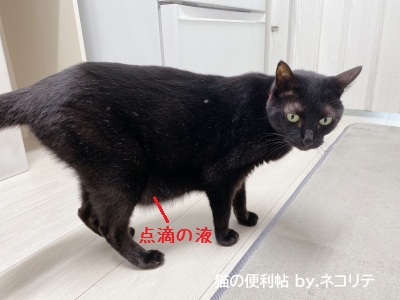
点滴をする理由は、体内の水分量を増やすことです。
水分が増える
↓
おしっこも増える
↓
たまった毒素や老廃物が体の外に出やすくなる(これが目的)
その結果、脱水の改善だけでなく、食欲の回復も期待できます。
【図解】点滴のしくみと誤解しやすいポイント
急性腎障害の点滴治療をわかりやすく説明すると、こんなイメージになります。
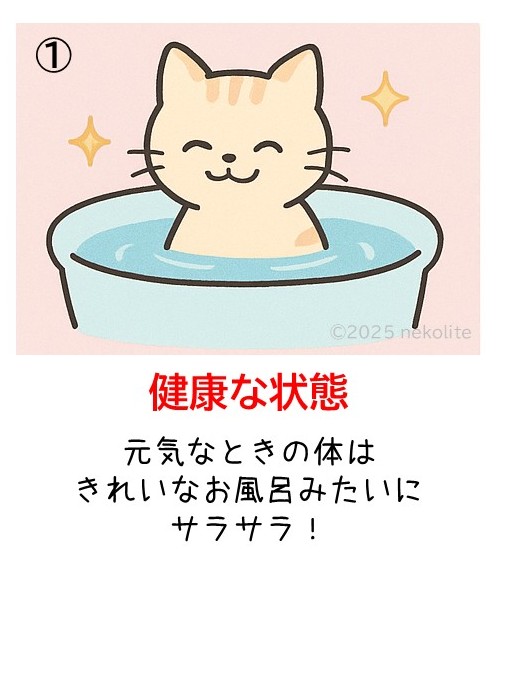
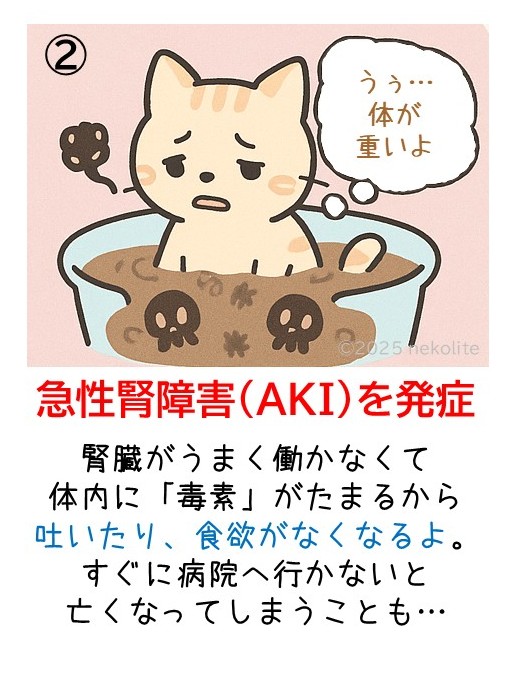
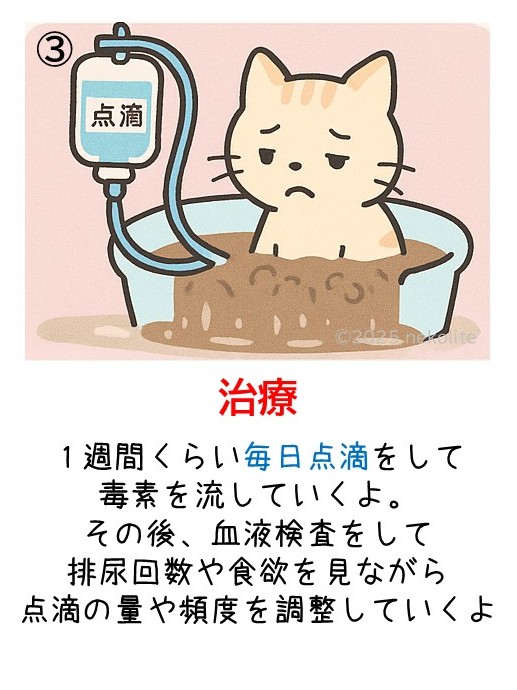
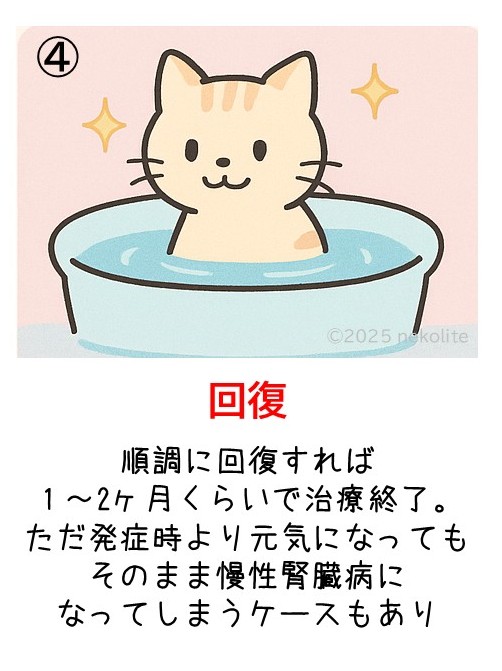
よく「点滴をしているから、ごはんを食べなくても大丈夫」と思われがちですが、それは誤解です。
実は、点滴はごはんの代わりにはなりません。
点滴の目的は、あくまでも水分補給。
食事のように栄養やカロリーをしっかり補うものではないので、体力の回復や維持には限界があります。
そのため、点滴をしても食欲が戻らない場合は、食欲増進剤を使ったり、強制給餌を検討したりすることもあります。

